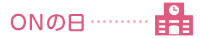学習塾・予備校市場では合併や提携の動きが活発。今後はIT活用の動きが焦点になりそう
学習塾・予備校分野では、東進ハイスクールなどを運営するナガセ、代々木ゼミナールなどを手がける学校法人高宮学園、学校法人河合塾グループ、駿台予備校で知られる学校法人駿河台学園という「4大予備校」グループに加え、市進ホールディングス、日本公文教育研究会などが大手。ベネッセホールディングスや学研ホールディングス、Z会グループなど、通信教育中心の企業も強い存在感を発揮している。一方、社会人向けサービスを中心に展開している企業としては、語学教室を展開するGABAやアルク、幅広い生涯教育講座を手がけるヒューマンホールディングスやユーキャン、資格取得分野を強化しているTACなどがある。
矢野経済研究所の「教育産業市場に関する調査結果2015」によると、2014年度における教育産業の市場規模は2兆5253億円で、前年度より0.6パーセント増だった。うち、「学習塾・予備校市場」「英会話・語学学校市場」「幼児英才教育市場」「企業向け研修サービス市場」「e ラーニング市場」「幼児向け英語教材市場」の6分野は拡大し、「資格取得学校市場」「資格検定試験市場」「カルチャーセンター市場」「幼児向け通信教育市場」「学生向け通信教育市場」「社会人向け通信教育市場」の6分野は縮小している。
全体の4割近く(9380億円)を占める学習塾・予備校市場は、前年度より0.2パーセント伸びた。ただし、好調な企業もある半面、生徒不足に悩むところも少なくない。今後は少子化が進むため、競争環境はさらに厳しくなりそうだ。こうした中、他社との合併や提携を目指す動きが活発化している。例えば12年3月には、「第一ゼミナール」を展開するウィザスが九州・沖縄で学習塾を展開する学習受験社を、ベネッセホールディングスが関西で学習塾などを手がけるアップを買収。13年8月には、学研ホールディングスが九州で学習塾を展開する全教研を買収した。営業エリアを広げて収益を拡大することと、幅広い年齢層向けのサービスを用意して「生徒の囲い込み」を目指すことが、合併・提携の主な狙いだ。また、14年8月、代々木ゼミナールが全拠点の約7割を15年以降に閉鎖することを発表したように、採算性の低い地域・事業から撤退するケースも目につく。
子ども向け教育市場では、ITを活用した指導方法が模索されているところ。公立の小中学校では、文部科学省が取りまとめた「教育の情報化ビジョン」に基づき、タブレット端末の導入が進行中。そこで学習塾などでも、タブレット端末を使った授業が広がりそうだ。今後は、デジタル教材やアプリの開発などでIT関連業界と協業する機会が増えるだろう。一方、インターネット経由で映像授業を流す低価格帯のサービスが登場し、既存の学習塾にとって脅威となっている。こうしたライバルに打ち勝つため、授業の魅力を高める工夫も必要だ。
社会人向け教育の世界でも、ITを活用した取り組みが盛んになっている。例えば、ベネッセホールディングスは15年4月、オンライン教育サービス「Udemy(ユーデミー)」を日本で提供開始した(下記ニュース参照)。「教育産業市場に関する調査結果2015」によれば、14年度における「eラーニング市場」の規模は前年度比15.7パーセントの大幅増。生涯学習に関心を持つ社会人は増えており、インターネット経由で手軽に学べるeラーニングへのニーズは、今後さらに高まると予測されている。
英会話・語学学校市場も堅調。社会人向け英会話サービスでは、インターネット電話などを使った安価なサービスが台頭し、既存の英会話スクールのライバルとなっている。しかし、企業のグローバル化を背景に、今後も成長が望めそうだ。また、小学校で英語教育が必修化されたことで、子ども向けの英語教育サービスも有望とみられる。
教育サービス業界志望者が押さえておきたいキーワード
大学入試センター試験に代わり、2020年から実施される予定。これまでのような「教科型」に加え、「合教科・科目型」「総合型」の問題を組み合わせて出題される予定。記述式の回答方法も導入され、思考力・判断力・表現力などを中心に評価する。学習塾・予備校は、対応を迫られる見通しだ。
ひと言で表せば「能動的な学習」。教える側が一方的に講義を行うのではなく、ディスカッションやプレゼンテーションなどを通じ、学ぶ側が能動的・主体的に参加するスタイルの授業形態。大学などで普及が進んでおり、アクティブラーニングにかかわる教材・学習システムへのニーズも高まるとみられている。
11年4月、公立小学校における「外国語活動」が必修化された。現在は5、6年生が対象だが、20年度には3年生以上が対象となる。「読む・聞く・書く・話す」に加え、英語で議論・交渉する能力を身につけることも重視される傾向。子ども向け英語教育市場は拡大が予想される。
このニュースだけは要チェック <買収や提携の動きには注目が必要>
・Z会グループの通信教育部門である増進会出版社が、「栄光ゼミナール」などの学習塾を手がけている栄光ホールディングスを買収。通信教育大手で大学受験に強いZ会と、小中学生向け学習塾大手の栄光ゼミナールが統合されることで、幅広い年代・対象の生徒を受け入れる体制が整う。(2015年8月7日)
・ベネッセホールディングスが、アメリカなどで人気のオンライン教育サービス「Udemy」を手がけるユーデミー社(アメリカ)と業務提携し、日本でのサービスを開始。教えたい人が講師として映像講座を公開できるオンライン型教育プラットフォームで、日本でも社会人を中心に多くの受講者が利用するのではと期待されている。
この業界とも深いつながりが<IT企業と協力して新サービス・アプリを作る機会が増えそう>
IT(情報システム系)
タブレット端末向け教材や学習アプリの開発などでの協力が進む
ゲームソフト
携帯ゲーム機向けに学習・知育アプリを開発するケースは少なくない
出版
大手通信教育系企業にとって、自社の出版部門は収益の大きな柱
この業界の指南役
日本総合研究所 シニアマネジャー 粟田 輝氏

慶應義塾大学大学院理工学研究科修士課程修了。専門は経営・事業戦略、各種戦略策定・実行支援や事業性評価。幅広い業界・規模の企業を対象としている。最近では、今後さらなる発展が期待されるブラジル市場に注目し活動中。
取材・文/白谷輝英 イラスト/坂谷はるか